第18 回日本抗加齢医学会総会 理事長提言② 実験室から臨床へ発展を遂げたアンチエイジング医療
- 抗加齢医学を知る
- 2019年4月1日
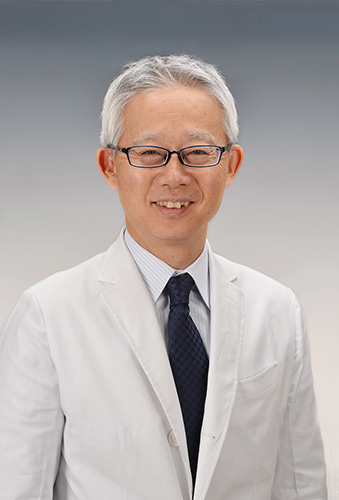
アンチエイジング医学はここ5年ほどで急速に進歩し、今までの実験室研究から臨床へと大きな発展を遂げています。具体的な例として挙げられるのが、老年のネズミと若いネズミのおなかの血管をつなぎ合わせた実験です。老年のネズミの血管が太くなり、神経幹細胞が増殖し、嗅覚が発達、骨格筋も再生しました。原因となる分子「GDF-11(GrowthDifferentiation Factor-11)」も分かってきて、今はどうやってこのGDF-11を活性化できるかについて、多くの企業が注目しています。現代の医学は「サイロエフェクト*」に陥っていますが、研究されたサイエンスを社会実装するためには、知を共有してサイロに横串を刺すことが必要で、まさに抗加齢医学会のミッションではないかと思っています。
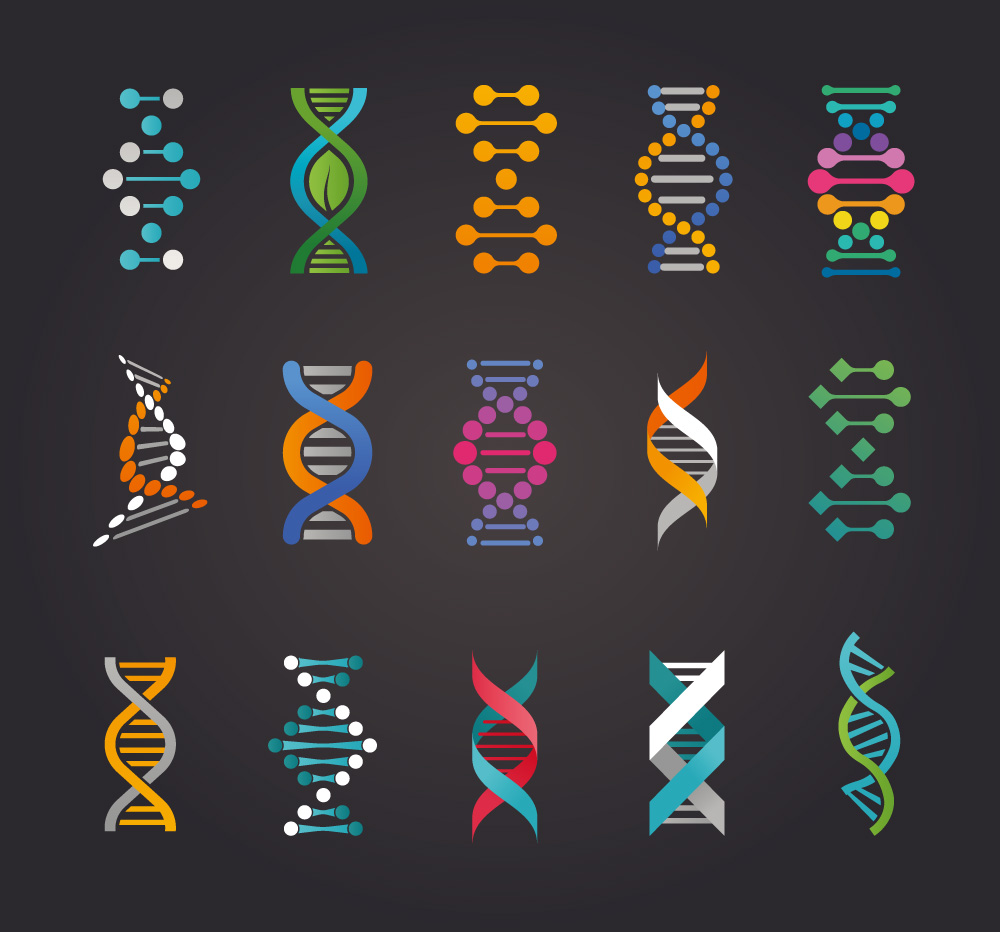
抗加齢医学が今後、注力していくことの1つにゲノム医療があります。疾患にかかりやすいか、かかりづらいかということを簡単に評価する方法として、「一塩基遺伝子多型」があります。遺伝子のある部分だけが違うことでアミノ酸の組成が変わり、タンパク質の働きが若干違ってくる。このことがいろいろな体質の違いに関係していることが分かり、さまざまな疾患に関連する遺伝子多型も具体的に分かってきているのです。
前立腺がんは男性が罹患する一番多いがんで、2000年から2020年の20年間で約3倍に増えています。疫学的には牛乳の消費量が多い国では前立腺がんの発生が多く、牛乳に含まれる動物性脂肪が関係していることが考えられています。この前立腺がんに関しては、すでに76個の遺伝子多型が同定されています。この遺伝子多型を1%持っているか10%持っているかで前立腺がんになるリスクが変わってくる。つまり遺伝子多型を調べることによってそのリスクを事前に把握し、介入することが可能になります。
アメリカでは、医療従事者が職種を超えてチームを組み個別データを活用しながら、がん領域における「スマートケア」という医療が発達しています。機能性食品や運動、ストレスマネジメントによって、遺伝子発現を変え、がんを予防したりがんの進行を遅らせたりする試みです。アンチエイジングのプログラムによって疾患の予防ができる時代になってきており、医療費を削減する有力な方法としても注目されています。
アメリカでもベビーブーマー世代が65歳以上の老年期に入り、アンチエイジング分野の市場拡大は確実といわれています。老年期人口が増えるからこそ、新しい技術・商品開発が求められています。姉妹団体の日本抗加齢協会は日本抗加齢医学会と協力して、アンチエイジングを企業や一般の方々に普及啓発するということを行っていますが、その中で機能性表示食品制度に対する支援も行ってきており、この制度の定着に大きく貢献しています。
抗加齢医学会の対象は年齢を問いません。生まれた瞬間から抗加齢医学はスタートします。遺伝子の表現型を改善することも抗加齢医療の対象であり、高齢者の社会参画を阻む要因である身体的・精神的な問題を解決することもアンチエイジング医療であり、これによって「抗介護」の効果もあります。
また、組織、地域における健康度(ソーシャルキャピタル)もアンチエイジングの重要な要素となります。社会の幸福感は、支えあうアンチエイジングから始まる。坪田前理事長が提唱したセルフ・アセスメントである「ごきげん」に加えて、わたしはピア・アセスメントである「はつらつ」を提唱していきたいと思います。
加齢そのものが遺伝子異常を起こして病気になりますが、遺伝子異常を防ぐメカニズムが解明され、遺伝子素質に基づく予防医療も期待されているなか、抗加齢医学こそが「はつらつ」とした快寿社会の実現をサポートできるのではないかと考えます。
※この内容は、第18回日本抗加齢医学会総会(2018年5月25日)で発表されたものです。
