2024年度 第2回日本抗加齢医学会 WEBメディアセミナー (2024年 12月4日)ダイジェスト
- イベントレポート
- 2025年1月8日

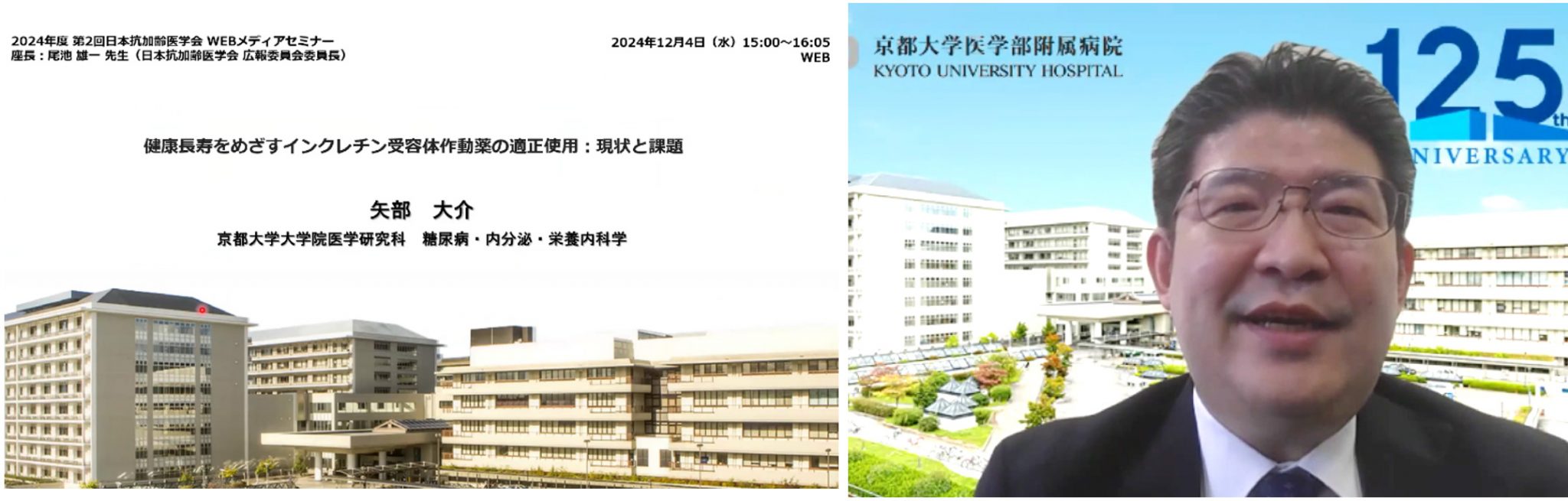
インクレチン受容体の中で、チルゼパチドは食欲の抑制効果が大きいとされています。これを打った上で食事をすると、体重が大体6ヶ月で10~15%、100kgの人であれば10~15kg痩せることができます。そのほとんどは脂肪が減って痩せますが、高齢者がこのような薬剤を使用するとサルコペニアやフレイルを助長するので注意が必要となります。また、ストレスを感じて食べてしまうタイプの方は、体重が減りにくいことがわかっています。そういう方々は、カウンセリングなどでしっかりと悩みを解決してもらうことも大切です。
GLP-1は、脂質異常や高血圧など、代謝に良い効果があります。このGLP-1受容体作動薬を使うと、主要心血管アウトカムのリスクを10~20%ほど軽減し、心血管死を14%、心不全の入院を13%、総死亡率を13%と、それぞれのリスクを減らすことが報告されています。また、GLP-1受容体作動薬と比べて、GIP/GLP-1受容体作動薬のチルゼパチドは総死亡率をより改善することがわかっています。主要な心血管イベントの発生なども軽減することが報告されていますので、上手に使うことで、健康寿命の延伸を図ることが期待されます。
一方で、GIP/GLP-1受容体作動薬について、人に長期間使用した際の安全性はまだ確立されていないため、10年ほど使用した上で安全性の確認をすることが大事です。重要な点として、高齢となり体重が減って、サルコペニアやフレイルが進んだ状態でこのような薬剤を使うと、より悪化し、死亡例も出てきますので注意が必要です。また、GIP/GLP-1受容体作動薬を含めて多くは注射薬です。注射薬は、インスリンよりも減量効果があり良いのではないかと思われがちですが、インスリンを止めてはいけないインスリン依存状態と呼ばれる方々に対しては、死に至ることもあります。
このインクレチン受容体作動薬は、減量効果の大きい薬剤です。国内でも肥満症に対して承認が得られていますが、肥満症というのは、糖尿病や高血圧症といった健康障害を伴う場合の肥満を指しますので、単に体重が重いので痩せるために使用するということはできません。さらに、若い女性たちが痩せるためにこの薬剤を用いるケースが事故に繋がっており、そのような目的で使用する薬剤ではないということをご留意いただきたいと思います。
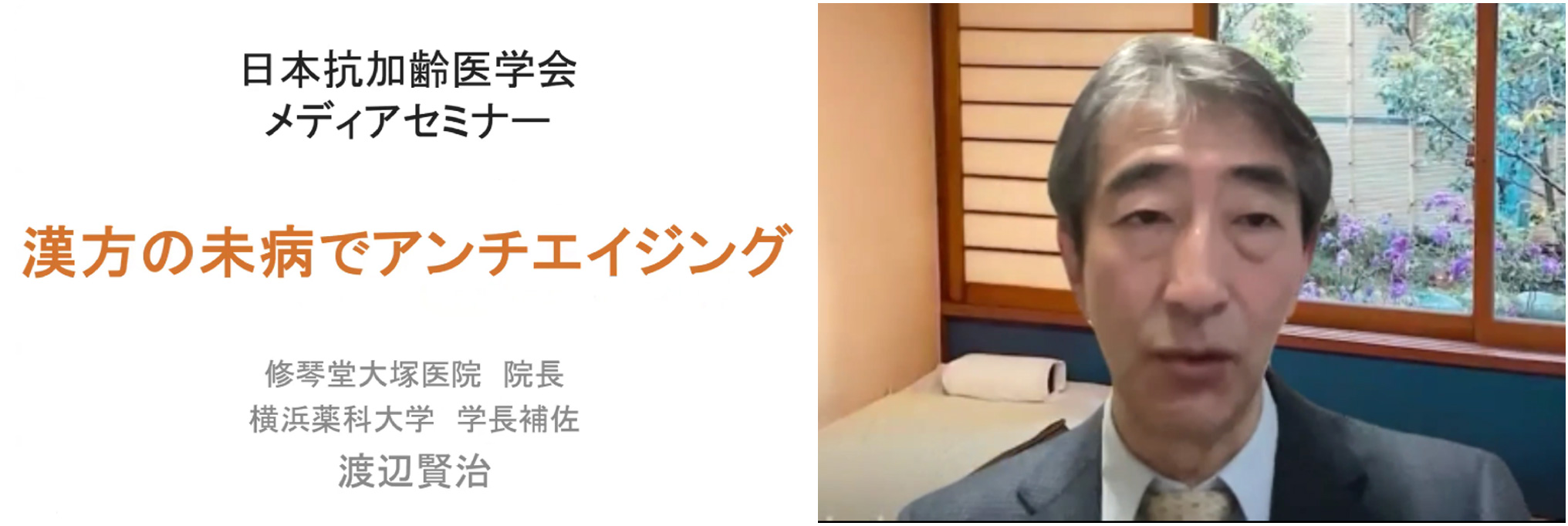
未病には、症状を有する未病と、無症状の未病の二つが存在すると考えています。症状を有する未病というのは、“何となく不調”と表現されますが、日々100%のパフォーマンスを出せる人はほとんどいないと思います。このような日常生活を送る上での不調を“何となく不調”といって、これが漢方の治療対象としてよくメディアに取り上げられています。例えば、疲れやすい、朝起きづらい、イライラしやすい、このような症状は病院に行っても、特にこれといった病名は診断されません。ただ漢方だと、漢方的診断がつき、それぞれに対して治療する薬があります。
恐ろしいのは無症状で潜行する未病です。これは老化に近く、例えば健康状態で生活していたのに心筋梗塞や脳梗塞などでとうとう病気になったと多くの人は話をします。薬を山ほど飲み、コレステロールを下げ、血圧を下げていますが、とりあえず薬でコントロールをできていれば自分は健康だと思っていた人が、ある日突然に心筋梗塞や脳梗塞になるというわけです。しかし、これは突然発症したわけではなく、日々身体に様々な変化が起きている上での最終段階ということになります。
目に見えない未病とどう戦うかというと、この未病がどのような段階にあるのかを知らないと、対策が見えてきません。そこで、アンチエイジングドックというものがすでに開発されていて、このアルゴリズムは同志社大学の米井嘉一先生(同志社大学大学院生命医科学部 教授)が長年蓄積したデータから作ったものになります。検査は、約1時間半で全て終わります。筋年齢、骨年齢など、同じように老化する人はいないので、個人の弱点を見つけどのように克服するか把握することが、一つの目的になります。
抗加齢は病気の予防に繋がり、漢方の未病の考えに近いものです。アンチエイジングドック≒漢方未病ドックで将来の病気の予測が可能になり、また体内で密かに進行する病気を見つける検査が少しずつ可能になってきました。

男性更年期障害とは、医学的にはLOH症候群(加齢男性性腺機能低下症候群)として我々は捉えています。その定義として、染色体異常、遺伝子異常、あるいは精巣の傷害、腫瘍、機能異常、および中枢神経系などの疾患に起因するものではなく、主として加齢、あるいはストレスに伴うテストステロン値の低下による症候群であり、数多くの機能障害をきたす病態とされております。
昨今の社会問題となっているプレゼンティズムは、いわゆる出社しているにも関わらず、心身の健康上の問題があり、業務上のパフォーマンスが上がらない状態というのは、健康経営を目指す企業にとって経済的な損失が非常に大きいという点で問題視されております。例えば、仕事に強いタスクがかかると、今日は体調が悪いから休んでしまおうと書類仕事に手がつかず、ネットサーフィンばかりやってしまうようなケースです。そのバックグラウンドには、テストステロンの低下から起こる男性更年期障害、いわゆるLOH症候群が隠れていて、年齢によって更年期障害を持っている人の割合は増えていきます。特にストレスが大きくかかる50代では、約45%の方は何かしらの更年期障害による症状があると言われています。
受診に訪れる患者を調べてみると、自覚症状のある方は4割程度で、メディアで男性更年期障害が取り上げられたことがきっかけで訪れる方も多くいます。実際、どの科で受診されているかというと、泌尿器科は6%ほどしかおらず、多くの患者は内科や精神科、心療内科を受診している実情があります。また、6割は医療機関で受診をしないという実態があります。テストステロンは爪や毛髪、唾液のなどから簡便に測ることができますが、それぞれに一長一短があります。
治療においては、テストステロンの補充療療法を第一選択として考えますが、日本ではテストステロンの注射剤を投与されることが一般的です。その他にも、生活習慣と密接に関係しており、漢方やビタミン、亜鉛などのサプリメントを投与したり、エクササイズを推奨して運動不足や肥満によるテストステロンの低下を防いだり、食事療法などがあります。また、ストレスを解消するようなマインドフルネスやリラクゼーションも重要になっています。
<2024年度第2回メディアセミナーはこちら>
<2024年度第1回メディアセミナーはこちら>
<2023年度第4回メディアセミナーはこちら>
<2023年度第3回メディアセミナーはこちら>
<2023年度第2回メディアセミナーはこちら>
<2023年度第1回メディアセミナーはこちら>
<2023年度特別企画 メディアセミナーはこちら>
<2022年度第4回メディアセミナーはこちら>
<2022年度第3回メディアセミナーはこちら>
<2022年度第2回メディアセミナーはこちら>
<2022年度第1回メディアセミナーはこちら>
<2021年度第5回メディアセミナーはこちら>
<2021年度第4回メディアセミナーはこちら>
<2021年度第3回メディアセミナーはこちら>
<2021年度第2回メディアセミナーはこちら>
<2021年度第1回メディアセミナーはこちら>
<2020年度第3回メディアセミナーはこちら>
<2020年度第2回メディアセミナーはこちら>
<2020年度第1回メディアセミナーはこちら>
<2019年度第2回メディアセミナーはこちら>
<2019年度第1回メディアセミナー②はこちら>
<2019年度第1回メディアセミナー①はこちら>
<2018年度第4回メディアセミナー②はこちら>
<2018年度第4回メディアセミナー①はこちら>
<2018年度第3回メディアセミナー②はこちら>
<2018年度第3回メディアセミナー①はこちら>
<2024年度第2回メディアセミナーはこちら>
<2024年度第1回メディアセミナーはこちら>
<2023年度第4回メディアセミナーはこちら>
<2023年度第3回メディアセミナーはこちら>
<2023年度第2回メディアセミナーはこちら>
<2023年度第1回メディアセミナーはこちら>
<2023年度特別企画 メディアセミナーはこちら>
<2022年度第4回メディアセミナーはこちら>
<2022年度第3回メディアセミナーはこちら>
<2022年度第2回メディアセミナーはこちら>
<2022年度第1回メディアセミナーはこちら>
<2021年度第5回メディアセミナーはこちら>
<2021年度第4回メディアセミナーはこちら>
<2021年度第3回メディアセミナーはこちら>
<2021年度第2回メディアセミナーはこちら>
<2021年度第1回メディアセミナーはこちら>
<2020年度第3回メディアセミナーはこちら>
<2020年度第2回メディアセミナーはこちら>
<2020年度第1回メディアセミナーはこちら>
<2019年度第2回メディアセミナーはこちら>
<2019年度第1回メディアセミナー②はこちら>
<2019年度第1回メディアセミナー①はこちら>
<2018年度第4回メディアセミナー②はこちら>
<2018年度第4回メディアセミナー①はこちら>
<2018年度第3回メディアセミナー②はこちら>
<2018年度第3回メディアセミナー①はこちら>

