2025年度 第1回日本抗加齢医学会 WEBメディアセミナー (2025年 4月10日)ダイジェスト
- イベントレポート
- 2025年6月29日


日本人は、世界一睡眠不足な国民であると言われています。昼間に眠くなることは、日本人の場合は仕方がないと思っている方が多いのですが、国際標準ではそれだけで体調不良の兆候と言えます。平均睡眠量と国民一人当たりのGDPで各国を比較すると、経済的に豊かな国の方が眠っている傾向にあり、ヨーロッパなどは明らかに右肩上がりの強い相関が見えます。一方、日本はヨーロッパの平均値より一時間ほど短く、日本国民の睡眠は特異であると言えます。また、男女別の国民平均睡眠量を見ると、ほとんどの国で女性の睡眠量は長く、生物学的には恐らく女性の方が長く眠るようにできているように思えますが、日本では男女が最も大きく反転しており、特に女性が寝不足であるという点でも、特異な国であると言わざるを得ません。
睡眠をとらないと脳のパフォーマンスは悪くなり、一晩徹夜をすると血中アルコール濃度0.1%相当の完全に酔っ払っている状態となります。徹夜でなくても1日4時間睡眠を5~6日続けると、徹夜と同等の状態となり、1日6時間睡眠でも10~11日続けると徹夜と同じ状態になります。さらに性格にも影響が生じ、利他的行為は抑制され、感情の制御もできなくなります。この睡眠不足を含めた睡眠障害が慢性的に続くと、身体的な負荷がかかり、うつを始めとするメンタルの問題、メタボリック症候群、中高年以降では認知症のリスクが増え、免疫が低下するため感染症などにもかかりやすくなり、がんのリスクも増えると言われています。
睡眠の量だけでなく、睡眠の規則性や質も非常に大事で、レム睡眠のパーセンテージが1%減るごとに、認知症を発症してしまうリスクは12年間で9%も増加するという論文が出ています。また、睡眠時無呼吸は非常に恐ろしく、重症の無呼吸症候群の場合、約12年の間に致命的な心血管障害や心筋梗塞、大動脈解離や脳卒中などを発症し、命を落とす確率が20%近くまで上がります。
眠気には、徹夜明けのような眠気を引き起こす恒常性制御と、時差ボケに関係する体内時計による制御という、2つのメカニズムがあります。体内時計の中心的な役割を担っているのは、脳の視床下部にある視交叉上核です。目の網膜には、露出計のような働きをする特殊な細胞があり、ここにブルーライトに反応する仕組みがあります。この細胞が光の情報を感知すると、そのシグナルが体内時計に直接送られ、体内時計に影響を与えます。
朝に強いブルーライトが目に入ると、体内時計の針が進みます。逆に、夜から深夜にかけて強い光を浴びると、身体はまだ昼間であると錯覚し、体内時計が遅れてしまいます。夜のホルモンとも呼ばれるメラトニンは、体内時計に従って夜間に分泌されますが、夜に光が目に入ると、体内時計が遅れるだけでなく、メラトニンの分泌自体も直接抑制されてしまうことが知られています。このため、夜間の強い光は、睡眠にとって非常に有害であると考えられています。 脳全体には、覚醒を促進する神経細胞のグループが複数存在する一方で、睡眠を促進する神経細胞のグループも複数あり、これらが互いに直接あるいは間接的に抑制し合う神経回路を形成しています。この仕組みによって、覚醒と睡眠はまるでシーソーのように切り替わることがわかっています。
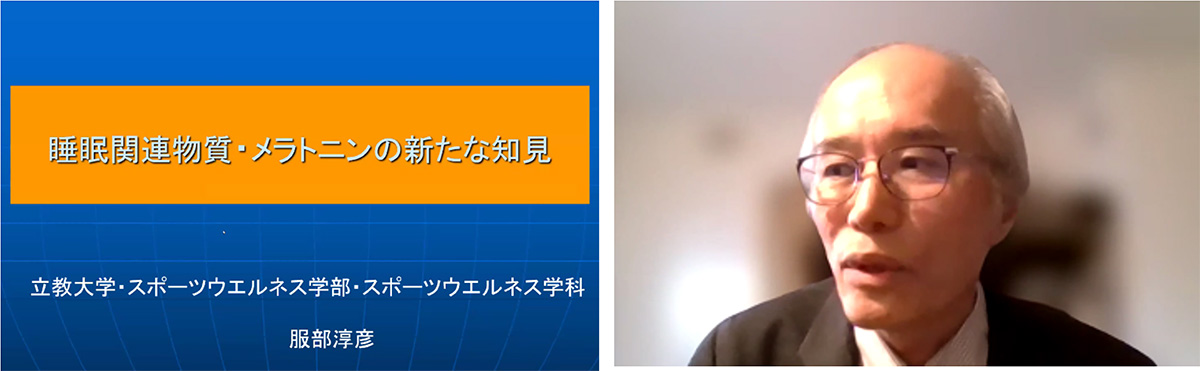
メラトニンは、非常に強力な抗酸化物質であり、活性酸素を除去する作用があります。さらに、直接的に活性酸素を消去するだけでなく、血中のメラトニンが受容体に結合することで、細胞内の抗酸化酵素の産生を促進するという報告もあります。このように、直接作用と間接作用の両方を併せ持つことから、メラトニンは非常に有望な抗酸化物質と考えられています。通常の薬とメラトニンを併用したケースに関する論文では、アルツハイマー病を患う一卵性双生児のうち、一方に3年間メラトニンを投与したところ、投与された側では脳の萎縮が抑制され、言語能力や歩行能力の数値も高く維持されたという症例報告があります。
メラトニンは肝臓で代謝され尿中に排出される一方で、脳内ではN1-acetyl-5-methoxykynuramine(AMK)に変化します。このAMKを一度投与するだけで記憶増強効果が得られることを発見し、米国および日本で特許を取得しました。さらに、若齢マウスを用いた物体認識試験により、AMKに記憶促進効果があることを検証しました。メラトニンからAMKへの変換に関与する酵素を阻害する阻害剤を投与することで、AMKの産生を抑制し、記憶力への影響を観察しました。その結果、阻害剤とメラトニンを同時に投与した場合にはAMKが産生されず、24時間後には記憶が保持されていませんでした。一方で、阻害剤とAMKを同時に投与した場合には記憶が保持されていました。この結果から、メラトニンがAMKに変換されなければ記憶の固定が起こらず、AMKが記憶固定に必須であることが示唆されます。
骨の形成や骨代謝とメラトニンの関係性を検証したところ、メラトニンは破骨細胞分化誘導因子を抑制することで、破骨細胞の増加を防ぎ、成熟した破骨細胞の機能を抑制することが分かりました。2010年の宇宙実験では、骨のモデルとしてほぼ同じ成分でできている魚の鱗が使われ、破骨細胞が宇宙に行くと、細胞は大きく変化し骨を溶かしていきます。ここにメラトニンが作用すると、元の大きさに戻っていきました。この結果は、宇宙飛行士の骨量維持に貢献できるのではないかと考えています。
骨の形成や骨代謝とメラトニンとの関係を検証した結果、メラトニンは破骨細胞分化誘導因子を抑制することで、破骨細胞の増加を防ぎ、さらに成熟した破骨細胞の機能も抑制することが明らかになりました。2010年に実施された宇宙実験では、骨のモデルとして、骨とほぼ同じ成分で構成される魚の鱗が使用されました。破骨細胞が宇宙空間に送られると、細胞は大きく変化し、骨を溶かす活性が著しく高まることが確認されました。そこにメラトニンを作用させたところ、破骨細胞は元の大きさに戻る傾向が見られました。この結果は、宇宙飛行士の骨量維持に対するメラトニンの有用性を示唆するものであり、今後の宇宙医学への応用が期待されます。

「第25回日本抗加齢医学会」では、生物学的年齢に焦点を当てます。暦による歴年齢と比較すると、生物学的年齢にはいくつかの特徴があります。歴年齢は時間の経過とともに自動的に加齢しますが、生物学的年齢は生活習慣や環境要因など、後天的な影響を強く受ける点が大きな違いです。近年、「老化」はさまざまな生体指標を用いて、より高い精度で定量的に評価することが可能になってきており、今回の学会では、海外からお二人の先生をお招きし、最新の研究成果をご紹介いただく予定です。
まず、Steve Horvath先生(Altos Labs, Cambridge, UK/Epigenetic Clock Development Foundation, Torrance, USA)は、DNAメチル化の加齢に伴う変化パターンに着目し、ユニバーサルクロックを提唱した、この分野のパイオニアです。次に、Mahdi Moqri先生(Harvard University, Harvard Medical School, Brigham and Women’s Hospital)は、従来のエピジェネティック指標に加え、新たなバイオマーカーを統合した総合的な評価手法を開発されており、臨床応用に向けたバリデーションの確立を担当されています。本セッションでは、両先生のご講演とディスカッションを通じて、生物学的年齢の測定技術の現状と今後の臨床応用について、深く掘り下げた議論が展開されることを期待しております。
もう一つの総会のテーマとして、「2050年の未来医療予測」を掲げ、医療技術、基礎医学、先進医療に加え、危機管理や地域医療といった幅広い視点から、各分野の専門家の先生方にご講演いただく予定です。危機管理に関しては、日本抗加齢医学会の会員でもあり、元パイロットとしての豊富な経験をお持ちの小林宏之氏(危機管理専門家・航空評論家)をお招きし、2050年を見据えた危機管理の在り方についてご講演いただきます。また、地域医療の分野では、高山義浩先生(沖縄県立中部病院 感染症内科)にご登壇いただき、2050年を見据えた在宅医療のあり方やその重要性についてお話しいただく予定です。
<2025年度第2回メディアセミナーはこちら>
<2025年度第1回メディアセミナーはこちら>
<2024年度第2回メディアセミナーはこちら>
<2024年度第1回メディアセミナーはこちら>
<2023年度第4回メディアセミナーはこちら>
<2023年度第3回メディアセミナーはこちら>
<2023年度第2回メディアセミナーはこちら>
<2023年度第1回メディアセミナーはこちら>
<2023年度特別企画 メディアセミナーはこちら>
<2022年度第4回メディアセミナーはこちら>
<2022年度第3回メディアセミナーはこちら>
<2022年度第2回メディアセミナーはこちら>
<2022年度第1回メディアセミナーはこちら>
<2021年度第5回メディアセミナーはこちら>
<2021年度第4回メディアセミナーはこちら>
<2021年度第3回メディアセミナーはこちら>
<2021年度第2回メディアセミナーはこちら>
<2021年度第1回メディアセミナーはこちら>
<2020年度第3回メディアセミナーはこちら>
<2020年度第2回メディアセミナーはこちら>
<2020年度第1回メディアセミナーはこちら>
<2019年度第2回メディアセミナーはこちら>
<2019年度第1回メディアセミナー②はこちら>
<2019年度第1回メディアセミナー①はこちら>
<2018年度第4回メディアセミナー②はこちら>
<2018年度第4回メディアセミナー①はこちら>
<2018年度第3回メディアセミナー②はこちら>
<2018年度第3回メディアセミナー①はこちら>

